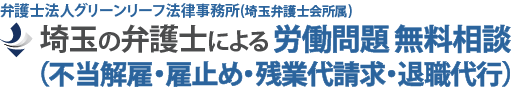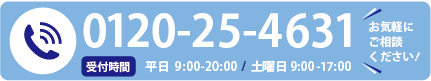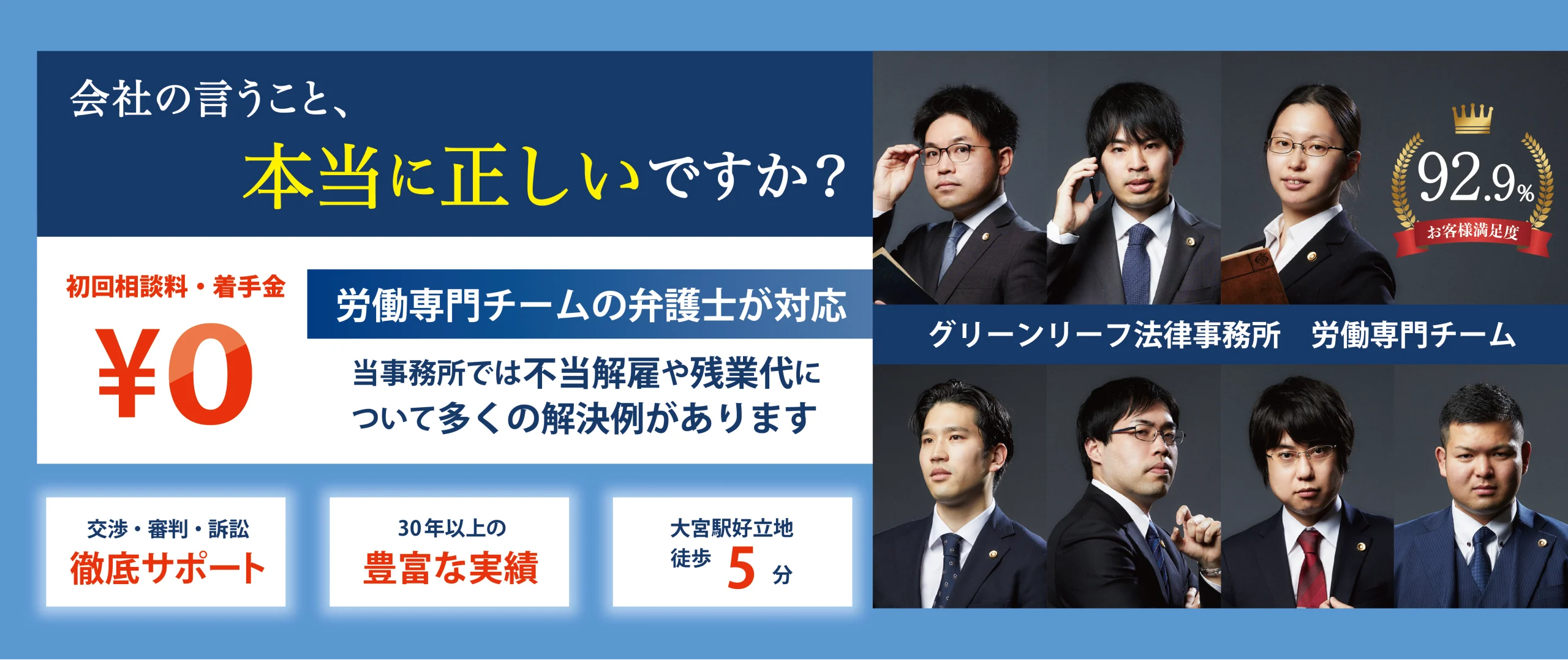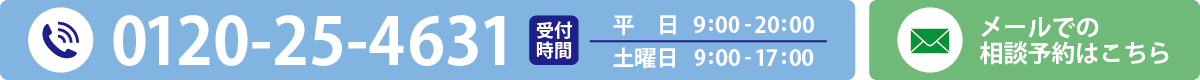ケガや病気を理由に会社から解雇されたり、退職を要求された場合、労働者として以下の対応を検討することが重要です。
解雇には制限があり、休職制度を利用できることもある。
業務上のケガや病気の場合

労働基準法第19条第1項により、療養のための休業期間およびその後30日間は、原則として解雇が禁止されています。ただし、療養開始後3年が経過しても治癒しない場合、平均賃金の1200日分の打切補償を支払うことで解雇が認められることがあります。
他方、症状固定と言って、治療によってもこれ以上の改善が見られない状況に至ってから30日を経過した後は、上記の解雇の制限がなされなくなります。
しかし、病気やケガが理由ですぐに元の業務に復職できないとしても、しばらくの間以前よりも軽易な作業に従事すれば元の業務に復職できる可能性があるという場合には、会社の方がすぐに復職ができないことを理由に解雇することができないということがあります。
そのため、怪我や病気を理由に仕事ができない場合であっても、会社の解雇を争う方法はいくつかあります。
私傷病(業務外のケガや病気)の場合

法律上の明確な解雇制限はありませんが、例えば、病気やけがによる少ない日数の欠勤を理由とするような解雇は、客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性がない解雇として、解雇権濫用法理により無効とされる可能性があります。
他方、1か月や数か月に及ぶ休業が余儀なくされるような病気やけがについては、会社の方で休職制度を設けて、仕事を休めるようにしている場合がありますので、次に紹介する通り、就業規則や労働契約を確認して頂き、休職制度の利用を検討すべきです。
休職中は給与の支給はされませんが、健康保険の傷病手当金が支給されて、生活費を得ることもできますので、休職制度を利用できる場合はぜひ利用しましょう。
休職制度

会社の就業規則や雇用契約に休職制度が定められている場合、休職期間中の解雇は制限されることがあります。そのため、休職期間や復職の条件を確認し、休職制度を利用できるのかを確認しましょう。
次に、休職制度を利用していますと、休職期間を経ても、治癒が不十分で復職が難しいという場合、自然退職となります。そして、自分としては復職をしたいのに、病気からの復職を会社が認めない場合、以下の対応を検討することが重要です。
医師の診断書の提出
まず、主治医から復職可能である旨の診断書を取得し、会社に提出します。これにより、医学的に就労可能な状態であることを証明できる可能性があります。
産業医の意見の確認
会社が産業医の診断を求める場合、産業医の意見を確認します。産業医が復職不可と判断した場合でも、主治医の診断書と併せて再度協議を求め、復職可能性について議論できる余地があります。
軽易な業務やリハビリ出勤の提案
従前の業務が困難な場合でも、軽易な業務への配置転換やリハビリ出勤(段階的な勤務復帰)を会社に提案することで、復職の道を探ることができます。このような検討を会社が行わずに復職を認めない場合、会社の対応が違法であることを主張できる場合があります。
記録の保存
会社とのやり取りや提出した書類のコピーを保管し、必要に応じて証拠として活用できるようにします。
解雇手続きの適正性の確認

解雇には、30日前の解雇予告または平均賃金30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。これらが適切に行われているかを確認しましょう。
労働基準監督署や弁護士への相談
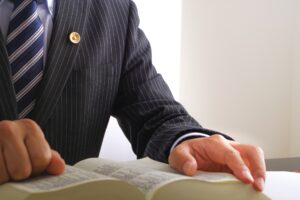
解雇が不当であると感じた場合、労働基準監督署や労働問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。専門家の助言を受けることで、適切な対応策を検討できます。
証拠の収集
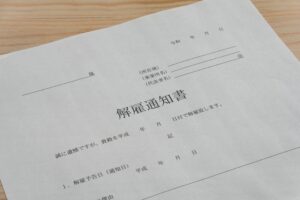
診断書、休業に関する連絡記録、解雇通知書など、関連する証拠を整理・保管しておくことが重要です。これらは、後の交渉や法的手続きで有用となります。
まとめ

病気やケガが理由で仕事ができなくなるということはどの労働者の方にも起こりうることですが、業務中に発生した病気やケガの場合は労働基準法による解雇制限がありますし、症状固定に至った場合であっても元の職務への復帰可能性を十分に検討しないまま会社が解雇した場合は解雇を争うことができる場合があります。
また、プライベートでの病気やけがであっても、休職制度により即時の解雇は回避できますし、休職中は健康保険の傷病手当金の支給を受けて生活費を賄うことができる可能性があります。
そして、休職期間満了時に即座に元の職務に復帰できない場合であってもしばらくの間軽易な作業を行うことで、復職ができる可能性があるという場合は、会社の方も即座に退職を要求できない場合があります。
このように、ケガや病気を理由とする会社の解雇や退職要求については、争う方法がありますので、お悩みの方は一度弁護士にご相談を頂けますと幸いです。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。